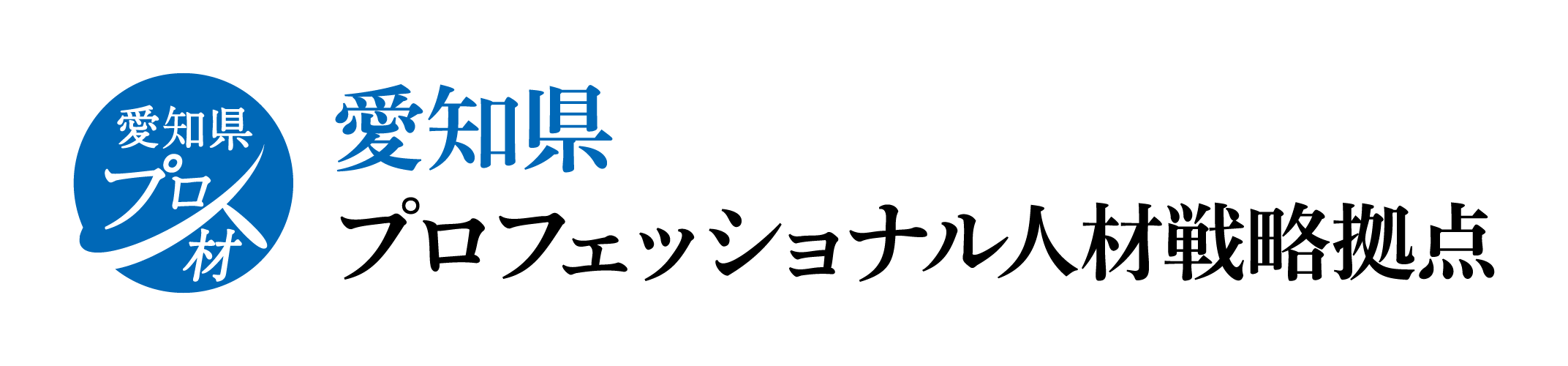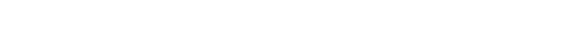人事ポリシー策定から、管理部門長採用と人事評価制度刷新までを一貫支援。
企業名:東海不織布株式会社
本社所在地:愛知県春日井市
事業内容:空調、液体濾過フィルター・自動車用内装材等に用いる不織布の製造・販売。
従業員数:25名
会社沿革
・1958年 創業。国内第一世代のニードルパンチ機械を導入
・1964年 衣類中綿等製品の製造を開始
・1973年 ロック製品(クッション、フィルター等の用途)の製造を開始
・1987年 手触り感を念頭に、欧州より起毛設備を導入
・1993年 欧州の展示会に出展された超音波接合装置を導入
・2000年 ロックシート製造法及びコルゲート折り法を開発し、設備設計、設置
創業以来、小規模ながらその機動力を活かし、世の中の小ロット、ニッチ色、風合等のニーズに応答してきた。SDGsにも積極的に取り組み、「モノ造り工程で発生している、副産物を活かした製品造り[SDGs#12]」、「養殖・鑑賞魚、廃液、ガス、下水道処理用フィルター用途として。[SDGs#6,14]」等、環境を意識したものづくりを推進している。
※当社主力製品である不織布「ロック」とその製造風景
代表者プロフィール
代表取締役 本多 利光(ほんだ よしみつ)

鉄鋼会社での勤務経験、子会社での経営経験を経て、2021年当社入社。同年10月より現職。就任より、「会社とは公器、世の中は無常、衆智をもって事に当たる。」を会社方針として掲げる。「経営デザインシート」を用いながら、抜本的な経営計画を敷き、社内改革を進めている。
副業人材プロフィール
楡井 三樹 (にれい みつき)(東京都在住)
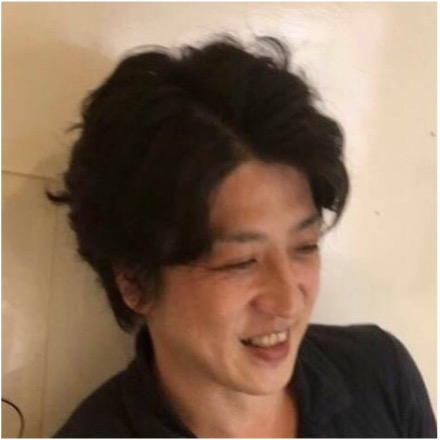
特定社会保険労務士として、人事の全領域を網羅し、経営理念や外部環境を踏まえた人事ポリシーの策定・実行を得意とする。IPO支援や人事制度の構築、エンジニア採用支援など、多岐にわたる実績がある。現在は、情報セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の運営会社LRMで人事責任者として邁進中。
——今回、会社として副業・兼業人材活用に取り組もうとした背景を教えて下さい。
本多 私は2021年3月に縁あって、事業を承継する形で当社に入社しました。当社の事務所と、2つある工場を自分の目で見て、社内のガバナンスの弱さや人材定着の悪さ、社員の高齢化に課題を感じていました。人事周りを中心とした社内整備に力を入れていくことが急務で、その先駆けとして管理部門長を採用し、あらゆる改革を推進していかねばならないと考えていました。また同時に、当社の人事評価制度については、恣意的に運用されていた実態がありました。これでは採用活動の際にも魅力にはならないため、正しく、給与・賞与に結びついた形にする必要がありました。当社のような製造業は、「設備」と「人」が大事ですが、総じて「人」の部分の体制強化が必要でした。
その頃、当社株主でもあり、普段より懇意にしている名古屋中小企業投資育成株式会社に相談をしたところ、愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下、愛知プロ人拠点)の紹介を受け、2023年3月に相談を受けることになりました。愛知プロ人拠点は、相談無料ということもあり、投資育成とともに、愛知プロ人拠点のサブマネージャーに来社していただきました。
——楡井さんは、どのような経緯で今回の副業人材の応募に至ったのでしょうか。
楡井 私はこれまで、IPO準備段階のベンチャー企業5社で、人事領域で勤務をしてきました。多様な企業で経験を積み、柔軟に対応できるスキルと幅広い引き出しを持っていることを強みにしています。コロナ禍でリモートワークが浸透した頃に、副業人材を斡旋するプラットフォームのことを知りました。まだ現在の仕事にも余裕があり、東海不織布さんのように、地方の企業で人材採用や人事制度のノウハウがない先において力を発揮しつつ、私も新たな経験を積めたらと思い、案件を探していました。お金目的だけではなく、実績づくりや今後に活かせるヒントを得たいとも思っていました。たくさんの経営者の方針を知れる機会としても考えていました。
また、東海不織布さんが、採用だけ、人事評価だけ、というわけではなく、両方のポジションで募集をしていたことに魅力を感じました。私が持つ人事領域全般の経験を活かすことができ、適任だと思い応募しました。応募後の面談では、本多社長の変革に対する熱意を感じて、一層力になりたいと感じました。
——募集から契約に至るまでの流れを教えて下さい。
本多 2023年3月に愛知プロ人拠点との初期相談を行い、6月に副業人材会社を実際に利用してみることにしました。選択した副業人材会社は、オンライン座談会の形式で、たくさんの応募者からいろいろな意見を聴取できるよい仕組みがありました。求める人材像の定義は愛知プロ人拠点のサポートも得られたので、負担はあまり感じませんでした。こういう出会いの場があるのか、と時代が変わったと感じました。その後、楡井さんと契約させていただき、2023年11月から勤務開始していただいています。
楡井 オンライン座談会では、東海不織布さんが持つ課題や、目指す方針をプレゼンテーションで詳しく聞け、熱意を感じることができました。他の参加者の意見はやはり参考になりました。応募者からすると、大人数での面談はアピール時間が限られていて、難しさは感じました。
——勤務開始後、どのような体制で業務にあたっているのでしょうか。
本多 勤務開始にあたって、最初は楡井さんに当社へお越しいただき、社内を一通り見学していただきました。以後の進め方についても楡井さんにリードしていただきました。管理部門長採用のテーマでは、社長の他、2つある工場の管理者2名と実務を担うスタッフ2名の計5名のチームにし、人事評価制度については社長と実際の評価者2名の計3名のチームにて運用をしました。毎週水曜日の15時から、1時半定例のオンライン会議を設置し、1時間半のうち、前半を管理部門長採用、後半を人事評価制度、という構成で進めることにしました。短い時間設定ですが、楡井さんのリードが上手く、時間が足らなくてオーバーしたことはほとんどありません。最初は週1回の会議で足りるかと思いましたが、実際にやってみるといいペースでした。週1の会議の間にもメールのやり取りや面接対応も挟んでいたので、不足は感じませんでした。
楡井 本業では裁量的な労働を認められていましたので、水曜日の15時〜という時間設定やメール等の対応も問題なく行うことができました。
本多 楡井さんが会議の司会進行とプロジェクトのマネジメントを行い、各会議の終わりには、楡井さん含めチームメンバーに、次回に向けての宿題を設定し、それを次回に持ち寄る形態にしました。資料はクラウドストレージを利用して共有する仕組みを取り入れていただいていつでも共有できる体制にしています。またオンラインミーティングのツールは当社がメインに使用しているMicrosoft Teamsを使用し、楡井さんにも合わせていただきました。

——契約後、現在までに行ってきたことの振り返りをしていただけないでしょうか。
本多 これも楡井さんが提示してくれたシナリオに従って進めていく形になりました。
楡井 まずは人事ポリシーの策定から行いました。人事ポリシーとは、すべての人事施策に一貫性と継続性を担保する基盤であり、考え方を定義したものです。人事関連の施策は、他の会社でうまく行った事例であっても、それをそのまま持ってきてもうまく機能しません。東海不織布の考え方はこうだから、採用はこうしましょう、評価はこうしましょう、という施策の作り方が必要です。フレームワークを用いてヒアリングして明確化していきました。
本多 人事評価については、基軸になる部分として、行動(コンピテンシー)と成果(具体的な課題テーブル)で評価することとしました。これは、ブレることがないように、結構な時間をかけました。これで現在の社員の評価をすると、理想と現実のギャップをはっきり認識することができました。これまで年功による評価が大きかったのですが、年功と求めるスキルが必ずしも一致しないということを、定量感をもって把握することができました。社員への説明会も実施し、運用に入っていくフェーズになっています。
管理部門長採用については、実際に採用することができ、勤務開始していただいています。現場のオペレーター採用の活動も並行して進めています。管理職向け、オペレーター向け、それぞれで活用すべき媒体の違いがあること、また単純に媒体に載せるだけではなく、いかにして知ってもらうかの工夫が必要であることを勉強できました。どのポジションの人が何を行うか整理できておらず、仕事の偏在が起きていたのですが、これも整理ができつつあります。
——一連の支援を通して、実感した効果や課題があれば教えて下さい。
本多 まずは何より、管理部門長採用が実現して、勤務開始していますし、人事評価制度も説明会を終えて実行段階までたどり着きました。楡井さんからは、お持ちの様々な支援メニューから、当社にとって最適なものを議論して選択していくという、型にはめない支援をしていただいています。オペレーター採用や人事評価制度の運用はこれからになるため、気を緩めず頑張っていきたいです。
楡井 今後、より良くプロジェクトを進めていくためには、ビジネスチャットツールの導入も検討していきたいと考えています。デジタル化やオペレーション支援も対応して、有効な支援を行っていきたいと考えています。
——最後に、これから副業人材活用に取り組もうと考えている企業へのメッセージをお願いします。
本多 世の中には優秀な人が、いっぱいいるのだと感じました。リモートでも十分に期待する機能を発揮できる時代になりました。コストパフォーマンスよく会社が進化できる新しい仕組みですし、ぜひご利用をおすすめしたいと感じました。
楡井 社内にないスキルを迅速に取り入れることができる良い仕組みだと思います。コンサルタントの活用に比べて、コストパフォーマンスを発揮できます。
一方で、情報管理や法令遵守は重要です。リスク管理はしっかり行う必要があります。
副業人材にとっては、プロジェクトを通じていく中で、会社の成長も促すことができ、自身の経験値も積むことができるため、今後ますます広がっていくものだと感じています。
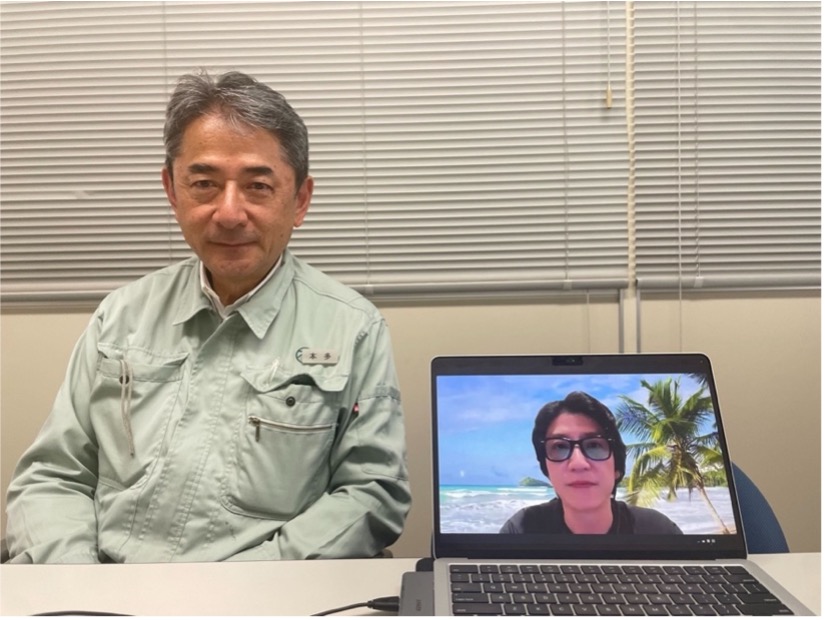
Copyright 2012 by AIBSC.JP All Right Reserved